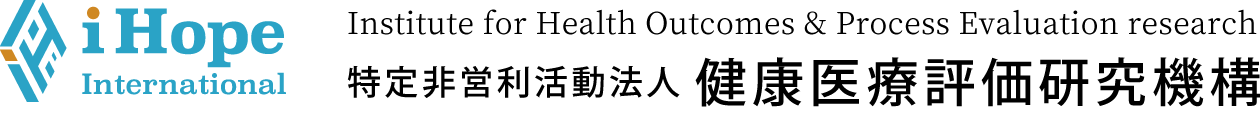事業紹介
「臨床研究の道標」
書評
(50音順)
- 秋澤 忠男 先生(昭和大学 医学部 内科学講座 腎臓内科学部門 客員教授)
- 上野 文昭 先生(米国内科学会 日本支部長)
- 岡田 浩 先生(カナダ Alberta大学 EPICORE Center リサーチフェロー)
- 菊地 臣一 先生(福島県立医科大学 常任顧問/ふくしま国際医療科学センター 常勤参与)
- 成田 有吾 先生 (神経内科専門医/三重大学 医学部 看護学科 教授)
- 野口 善令 先生(名古屋第二赤十字病院 副院長 兼 第一総合内科部長/救命救急センター長)
- 橋本 信夫 先生(京都大学 名誉教授/地方独立行政法人 神戸市民病院機構 理事長)
- 丸山 泉 先生 (日本プライマリ・ケア連合学会 理事長)
- 森田 学 先生(岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 予防歯科学分野 教授)
先生方、お忙しいところ書評をお寄せいただきありがとうございました。
今後も新しい書評をいただきましたら掲載いたします。
秋澤 忠男 先生(昭和大学 医学部 内科学講座 腎臓内科学部門 客員教授)
医療者の疑問の「心」をどう臨床研究として結実させるか
日々患者さんと接していると様々な疑問が生じてきます。現在の診断や治療法は適切だろうか? こうした方がより効果的ではないだろうか? でもどうやってそれを証明しようか? ちょっと考えてみたけれど、皆目見当がつかないし、やはり大学の偉い先生や企業の援助がなければ臨床研究は難かしいや。
多くの医療者がこうした思いをされたているのではないでしょうか。一方で、最近の臨床研究ブームから、データ収集や統計解析、論文執筆についてのハウツー本は多数出版されていますが、これらの本を読んで臨床研究が始められる訳ではありません。
本書は医療者の疑問の「心」、をデータ収集や統計解析につなげる「研究の基本設計図」を作り上げる過程を7つのステップで解説し、臨床家の「心」を自分たちの手で臨床研究として結実させることを目標に執筆されました。
著者の福原教授は「研究のための研究から医療を変える研究へ」をモットーに、京都大学にわが国で初めて設立された公衆衛生専門大学院でMaster program for Clinical Research (MCR)コースを立ち上げ、多数の若手研究者を育成する一方、2004年から「臨床家のための臨床研究デザイン塾」を毎年主宰し、100名を超える臨床家がその教えを受け、臨床研究に携わっています。
こうした豊富な経験から生まれた本書は、7つのステップに従って研究の入り口に到達するまでの技法が解説されていますが、各章には道標(みちしるべ)という囲みが配され、悩みの分岐点での対応に的確なアドバイスが記載されています。また去来夢(コラム)には関連するトピックスが休憩所として、さらに章末には復習用にまとめとクイズが配され、クイズの解説は読者限定のウェブサイトに掲載されるなど、新しい趣向も凝らされています。
多くの「心」ある臨床家の臨床研究の旅に、本書が活用されることを期待します。
(「腎と透析」 Vol.74 No.6 掲載)
上野 文昭 先生(米国内科学会 日本支部長)
日本は世界で第何位?
日本は世界有数の先進国である。経済大国であり先端技術でも世界をリードしている。ところが世界の一流医学雑誌に採択された日本発信の臨床研究は、世界で25位!という惨状である。しかも年々下降傾向にあるのは由々しき状況といえる。
では日本の医学は二流なのであろうか?否、ノーベル賞受賞者を輩出したことは記憶に新しい。臨床レベルだって決して世界に引けを取らない。問題はよい臨床研究が少ないことである。もっと正確に言えば、よい臨床研究を始めるためのお作法を知らな過ぎることである。
臨床研究を始めるにあたって
このたび上梓された『臨床研究の道標(みちしるべ)』を目にして、眼から鱗が何枚も落ちた。これぞまさに日本の臨床研究が世界レベルに一歩近づくための道標である。本書を読まずして臨床研究を始めることは、ルールを知らずにカジノでゲームをするぐらい無謀で虚しい挑戦である。
著者の福原俊一教授は臨床研究デザインの第一人者として多くの優秀な若手を育て日本の臨床研究のレベルアップに尽力されているが、実は単なる臨床疫学者ではない。彼は数少ない米国内科専門医であり、FACP(米国内科学会上級会員)の称号を有するグローバルに通用する内科医である。本書でも医療者の心が臨床研究の出発点であることが強調されている。類書と異なり、難しい統計学や臨床疫学の知識を押し付けるのではなく、医療者の疑問を解くために段々と知識を得たくなってくるような見事な流れである。
サービス精神旺盛の楽しい書
本書の内容は決して平易ではない。むしろ臨床医にとっては高度で難解である。でも全然そう感じさせない。研修医と謎の老人との対話に始まり、多くのイラストや有益な囲み記事をちりばめながら、読者を臨床研究のために重要な7つのステップへと引きずり込むことに成功している。一度読んで忘れたことでも二度、三度と読み返すのが楽しい。
読み終えた後の不思議な感慨
よい臨床研究をしたいという志のある医師にとって本書は必読の書である。また、臨床論文を正しく読みたいと願っている若手医師から指導医クラスまですべての医師に自信を持って推薦したい。本書に登場する研修医が最後に抱いた「期待感にちょっぴり自信のようなものが混じった、しかし静かで落ち着いて、ひと言で言えない感情」に、評者の私も共感を覚えた。
岡田 浩 先生(カナダ Alberta大学 EPICORE Center リサーチフェロー)
薬剤師としての自分の仕事が,本当に患者のアウトカムに影響を与えているのか,検証してみたいと思ったことはないだろうか?
では,そのような日常の臨床上の疑問をどのような形で検証するのか,言い換えればどのような研究デザインにするのかわからず途方にくれる人も少なくないのではないだろうか。
本書は,最も早くから研究デザインの重要性について提唱され,研究ばかりでなく学会などでリサーチデザインのワークショップなどの教育活動も積極的に実施しておられる福原俊一先生の最新刊である。
日常臨床における漠然とした疑問を,研究として調べ始める前に,まず研究の基本設計図を明確化した「7つのステップ」を使って磨き上げる手法を提唱している。
第1章には,研究を行ううえで陥りやすい間違い「7つのご法度」について紹介されている。詳しくは本書を読んでいただきたいが,「1.データをとってから研究デザインを考える」や「2.リサーチ・クエスチョンがあいまい・具体的でない」など,多くの読者にも心当たりがあるのではないだろうか。
内容はたいへん高度でありながら,わかりやすい図解の多用と,新人とベテランとの会話という形で説明されるなど,わかりやすくするための工夫が各所に凝らされている。そのため,類書にはない平明で明解な解説書となっており,臨床の現場で研究をしてみたいが,指導を受けることが難しかったり,最初の一歩がわからないという初学者にとって最適な本である。また,臨床研究についてすでに知識のある先生方にとっても,説明の切り口など,必ず新しい発見が詰まった本となっている。
実は私自身も,薬局での介入研究:COMPASSプロジェクトを始める際に,福原先生のご著書で勉強し,PICOをまず書いた経験をもっている。臨床研究に興味のある先生方は,ぜひ本書を一読してみることをお勧めする。
(株式会社じほう『月刊薬事』2013年6月号掲載)
菊地 臣一 先生(福島県立医科大学 常任顧問/ふくしま国際医療科学センター 常勤参与)
今は、EBM(evidence-based medicine)が臨床研究を実施する際の前提になっている。しかし、少し前までは、そんな認識は誰も持っていなかった。それだけでない。臨床家は、偏見を持ってEBMをみており、敵視さえしていた。今からみれば昔日の観がある。
勿論、医療がすべてscienceから成り立っているかと言えば、そうではない。EBMが明らかにしたのは、皮肉にもNBM(narrative-based medicine)の重要性である。医療は科学だけで成立し得るのか、という問いを投げ掛けられているのが現状である。
このような歴史を振り返って、この本を手にとる。すると、自分自身の臨床研究を巡る経験を、苦々しくも、懐かしく想い出される。一つは、データの不備による臨床研究の断念である。昔は、担当した患者の病歴や治療経過と最終的な治療成績を、暇を見付けて、1枚の紙に写し取り、それを手元に置いていた。普段の診療の中で、アイディアがふと湧き、休みを利用して蓄積した資料をめくる。そして、自分の仮説の妥当性を検証する為にまとめに入る。当時は、他の医師達も似たようなことをしていたのだと思う。しかし、遡って集計してみると、欲しいデータが欠落しているのである。そうなると、自分の仮説は推測の域を出ない。資料収集と仮説を立てその為に何が必要かの順序が、今考えると、逆であった。日常の忙しい診療のなかで、このような挫折が2、3回続くと、臨床研究を継続する意志を持ち続けるのが困難になり、ついには断念に追い込まれてしまう。
もう一つは、客観評価の視点の欠落である。自信を持って投稿した原稿が、自分には理解が出来ない理由で却下されてしまうのである。どうしても、その理由が理解できずに、海外の友人に専門家を紹介してもらい、どうにか出版にこぎつけたことがある。
これらの苦い経験を今の視点からみれば、私自身の、「臨床研究とは何か」、「臨床研究はどうするのか」という問い掛けに対して、系統立った教育を受けてこなかった故のことだと理解できる。
この本は、日常診療の中で、どのように診療していれば、独りでに(言い過ぎ?)、自分の診療上の疑問を、バイアス(この意味も今は理解できる)を排除して、アウトカム(この言葉の正確な意味が今はよく分かる)を提示できるかを可能にしてくれる。
この本の真の価値は、恐らく、臨床研究を始めようとしている人よりは、臨床研究をしている人や一度はしたことのある人に、極めて役に立つ。この本の内容で、この値段は高くない。臨床研究を始める前に1度読んでおくと後悔せずに済むし、一流誌に掲載される機会も格段に増すことは間違いない。
(株式会社医学書院「臨床整形外科」6月号掲載)
成田 有吾 先生 (神経内科専門医/三重大学 医学部 看護学科 教授)
さまざまな臨床研究解説書はある。しかし、これまで、研究の出発点である医療者の「心」と、実際のデータ収集との間にある技法を教えてくれる本はなかった。本書は、この医療者の「心」と「データ収集」の間にある「臨床研究のブラックボックス」についてわかりやすく解説した好著である。本書で扱っているのは量的研究、かつ臨床研究の本質を「比較すること」に置いている。頭の中の作業だけでは不十分であることも強調している、必ず紙やホワイトボードを使うことを提示し、かつ、具体的な臨床研究の「可視化」例を見せてくれる。
「臨床研究のデザインの旅」と銘打った部分では、読者に「臨床研究のリテラシー」習得の解説に、眠くならないような工夫をしている。実践演習として、ある「リサーチ・クエスチョン」を提示し、「研究の基本設計図」を7段階のステップにわけて、回答させる手法をとっている。各ステップの作業を読者が行いながらリテラシーを学習させて行く。
読者の理解助ける方略として、若手女性外科医のOlive、その臨床研究の師範(Mentor)である臨Qがマンガで登場する。若い世代の医師が引き込まれやすい雰囲気を醸成している。この臨Q師範は、どなたかの別の姿であることは読者にはよく判る。Fletcher先生の影響からアウトカム分類(臨Q編、p.112)を提示されている。7段階のステップは以前から著者福原俊一先生が提示されていた臨床研究の枠組みであり、詳細に説明されている。
各所に配置されている「道標」(みちしるべ)で、判断の分岐点での示唆が、「去来夢」(コラム)には解説と当該箇所の難易度が提示されている。読者がスムーズに、かつ限られた時間の中で、速やかに本書を読み終えるための工夫でもある。既に、福原俊一先生の著書をいくつか読み進めた読者には「道標」や「去来夢」をチェックして、必要なところのみを再度読み下すこともできる。個々の項目の解説もわかりやすく、自らの知識の再確認や、他者への説明、相談に際して、必要なところを辞書的に利用する方法もあろう。各所に配置された図も判りやすい。
「去来夢」の「ニワトリと卵」どちらが先に、の結論など、読み物としても面白い(p.63)。さらに、読者限定ウェブサイトが用意され、p.11にユーザ名やパスワードも提示されている。福原先生の、どうしても臨床研究のスピリットや本質を伝えたいという気概が伝わってくる。
第1章では、臨床疑問(Clinical Question, CQ)からリサーチ・クエスチョン(RQ)に構造化するプロセスを概説している。これは、良い素材(発想、CQ)をまな板にのせる前に「下ごしらえ」することと比喩されている。よく練られたRQができれば、研究の基本設計図は半分書けたも同然である。良いRQに求められる基準として「FIRM2NESS」を福原先生は以前から提唱されている。本書でも、あらためて詳細に解説されている。
第2章では、概念モデル作りの重要さ。臨床研究の基本的なお作法が展開される。第3の因子(予後因子、中間因子、交絡因子、効果修飾因子;p.65)を見つけるためにも有用である。統計専門家に相談する際にも、概念モデルは有効なコミュニケーションツールとなる(p.60~)。図示することは、他者への理解に役立つばかりでなく、研究を進める本人にも、理解を深め、自らのチェックにも非常に有用であることが示されている。例図としてはp.74.は判りやすい。
第3章では「測定」の重要性が説かれる。印象的なことばとして「測定できない概念はない」(Higgenbotham先生、Newcastle大学、CCEB).p.80は、定量的研究の心意気でもある。
第6章と第7章では、本書のハイライトである。著者が臨床研究の本質であると位置づける「比較」の解説が展開される。臨床研究デザインにおける努力の多くが、「比較の質」を高めることに費やされると言う。では比較の質とは何か、これを落とす原因は何か、そしてそれを高めるにはどうするか、がわかりやすく書かれている。これまで安易に使用されてきたバイアスという用語を、交絡と、交絡以外のバイアスに分けて、良くわかるように解説されている。
本書は、医師を念頭に書かれている。しかし、他の医療スタッフであっても、理解しやすく、大変参考になる。私の領域では、看護学修士のテキストとして活用できると考えている。
野口 善令 先生(名古屋第二赤十字病院 副院長 兼 第一総合内科部長/救命救急センター長)
本書は、今日読んで明日からすぐに仕事に使えるというFirst Aid的な内容の本ではない。そう期待して手に取った読者は、「どうしてデータ処理や統計学の話を最初に書いてくれないのだろう。それさえあれば、すぐに研究をまとめられるのに。」というもどかしさを感じるかも知れない。
本書の主人公である後期研修医のOliveは臨床研究がしたいのだが、師匠である臨Qになかなか始めさせて貰えない。臨QはOliveに研究を始める前に考えるべき課題をいくつも投げかける。Oliveはなぜ研究にとりかからせてもらえないのか不満を持ちつつも次第に自分が明らかにしたいことへの考えが深まっていく。
「ここに患者データがあるからこれで何か研究まとめて」上司からこう言われた経験のある読者はいないだろうか。筆者も時々こうした研究の相談を受ける。しかし、本書を読めば、こうしたやり方で行った臨床研究が魅力的なものにならないのはなぜかが理解できる。世の中を突き動かすような臨床研究のもとになる疑問は現場の当事者のみが産み出せるもので、さらに漠然とした疑問をリサーチクエスチョンとして洗練させ、仮説に昇華させるというプロセスを経ない研究は説得力をもって他人を動かすことはできないからである。
本書には、臨床研究7つの御法度として最初に、『データを取ってから研究デザインを考える(泥縄)』があげられている。この「とりあえずデータ集めとけば何とかなる」病は、日本の医学界だけでなく世界中のどの業界でも世界中で蔓延している根の深い病気のようである。たとえば筆者は、診断推論の領域で鑑別診断を考えないでまず検査をしようとする態度を『どうしてこの検査やってない症候群』として批判したが1)、両者は仮説を作らずとにかくまずデータを集めようとする点で、共通の病理構造を持っていると言ってよい。
もし読者がOliveと同じもどかしさを感じたとすればそれは本書が投げかけている問題にどっぷりつかっているということである。研究を始める前に本書の1-3章をじっくり読んで考えることによって小手先のやっつけ仕事ではなく真に他人の興味をひく臨床研究が可能になるだろう。
もちろん後半に、臨床研究に必要な臨床疫学や生物統計学の知識もわかりやすく(しかも斬新な視点から)まとめて書かれているが、筆者は、研究を始める前の部分こそが本書の真髄であると思う。
このように、臨床研究に興味のある人には必読の書であるが、臨床研究に興味のない人には効用はないのだろうか。そんなことはない。本書が訴える内容はいろいろな分野の活動に応用できる。1章に『良いリサーチクエスチョンはFIRM2NESSであることが求められる』と書かれているが、これは、ビジネスや教育の世界のSMARTの法則、RUMBAの法則とも共通する測定可能、具体的、実施・達成可能などの概念を中心に構成されている。自分の考えていることをいかに見える化、言語化して、他人と共有するかというプロセスは複数の人間がチームを作って共同作業をする際の基本である。そのため、病院内でプロジェクトを遂行する立場にある人、診療所のマネージメント上の問題を解決しなければならない人などにも有用である。本質を見極める能力を磨くという意味では下手なビジネス書を読むよりも役に立つかもしれない。さらに、日常的にいろいろな問題をより具体的に考える態度を身につけることで臨床医の臨床能力に資することができる。たとえば、「○○病に△△治療するとよくなる」とあいまいに考えず、どんなアウトカムがどのように良くなるのかとPICOを深く考える習慣をつけるだけでも臨床能力は格段に向上するだろう。
最後に、社会に貢献できる臨床研究こそに意味があるという哲学が全体の底流となっていて読者の胸を打つ。類書にたとえれば哲学がある点はRothman本2)に比肩されるが、Fletcher本3)に似た臨床医への優しさも感じられる。本書が日本のFletcher本になって臨床研究のみならず、日本の医療の質の改善に貢献することを切に望むものである。
- 注)
-
- FIRM2NESS
-
- F:Feasible(実施可能性があり)
- I:Interesting(真に興味・関心のあるテーマで)
- R:Relevant(切実な問題で)
- M:Modifiable(要因やアウトカムが改善可能な)
- M:Measurable(測定可能な・可視化できていて)
- N:Novel(新奇性があり)
- E:Ethical(倫理的で)
- S:Specific(具体的で・絞り込まれている)
- S:Structured(構造化された)
-
- SMARTの法則
-
- S:Specific 具体的
- M:Measurable 測定可能
- A:Achievable 達成可能
- R:Relevant 関連性がある / Result-oriented 結果志向
- T:Time-bound 期限付き
-
- RUMBAの法則
-
- R:Real 現実的である
- U:Understandable 理解可能である
- M:Measurable 測定可能である
- B:Behavioral 行動可能である
- A:Achievable 達成可能である
- 文献
-
- 1)野口善令 どうしてこの検査やってない症候群 medicina 48(9) 1526-1529 2011 医学書院
- 2) Robert H. Fletcher 臨床疫学―EBM実践のための必須知識 メディカルサイエンスインターナショナル2006
- 3) Kenneth J. Rothman ロスマンの疫学―科学的思考への誘い 篠原出版新社 2004
橋本 信夫 先生(京都大学 名誉教授/地方独立行政法人 神戸市民病院機構 理事長)
改めて福原先生の頭脳の中を垣間見させて頂いた思いと、先生がこれまで培ってこられたものの深さと広さを感じさせてくれます。
丸山 泉 先生 (日本プライマリ・ケア連合学会 理事長)
本書は、道標(みちしるべ)とタイトルにあるように、臨床研究のステップを7つに分け、読み進めていくうちに大枠の理解が可能となるよう、巧みに設計されている。一度目は流し読みでよいので最後までともかく読み進めるとよい。そうすると、二度目には、かなり深く理解できたことが自覚できる。臨床研究を意図した時に、おそらく多くの人がどうすべきかと迷う事柄についても、それぞれの分岐点での対応の道標が書かれている。
ともすれば、自分なりの脆弱な臨床研究のデザインを描き、拙速にデータ収集に取りかかり、実は曖昧なデータにもかかわらず、統計解析の技法そのものにこだわるという、負の連鎖に陥ることがある。大枠のデザインの善し悪しを吟味することなしに進めてしまう前に、本書に書かれている臨床研究の骨格のあり方をまず理解しておくことが結局は早道であり、他者の評価に耐え得る研究となることは間違いないであろう。
学会の臨床研究の将来について、長い間、研究という世界からはなれていた私なりに方向性を模索していた時、本書を手にすることができた。福原先生の序文に本書の意図するところは十分に書かれている。臨床研究の成功の要点は「研究の出発点である医療者の心と、実際のデータ収集・解析や論文化の間にある」と明確に述べられている。臨床の現場にある者が、志といってもいいだろう、「さて」、「いざ」と心を奮い立たせるだけで、評価に耐え得る臨床研究の結果を出すことは困難である。もちろん、その志はきわめて大切なのではあるが、志と外部評価を一致させていくことは学会の使命でもある。
本書は、若手外科医であるオリーブと臨床研究メンターとの質疑応答で話は進められていく。中には概念とは何かという難しい問いかけもあるが、平易に理解できるような工夫が散りばめられている。たまたま平行して、「統計学が最強の学問である」(西内啓)を読み進め、より強く思ったことは、比較の質である。未来のために、プライマリ・ケアの現場から確かな証左を出していかねばならない私たちにとって、また、新しい分野に明確に踏み出そうとしている若い臨床医にとって、もっとも重要なことと考えている。ぜひ一読していただきたい本書である。
(日本プライマリ・ケア連合学会誌 掲載)
森田 学 先生(岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 予防歯科学分野 教授)
経済分野のみならず,学問領域における日本の衰退と隣国中国の台頭が著しい.これに対して,安部政権は医療分野にテコ入れし,日本の武器の一つとして世界に発信することで日本の存在感を示したいようだ.ところが,この医療分野において研究の量・質ともに出遅れしているのが「臨床研究」である.既に中国の後塵を拝していると危惧する声も聞く.逆に言えば,今後の充実が最も期待されている分野なのだ.
筆者は京都大学で医療疫学を専門とする内科医である.本書には,日本における臨床研究の推進役であり,かつ同分野の人材育成を担う草分け的存在でもある筆者のメッセージが随所に散見される.日ごろの臨床で疑問に思っていることを自分の力で解決したいと感じている人たちが最初に読んで欲しい指南書といえる.疫学の専門書にありがちな難解な標記を可及的に減らし,その道の達人(臨Q老人)とOlive(おりべともこ 後期研修医)とのテンポよい会話を通じて,読者の興味と理解をどんどんと深めていく.冒頭に書かれているのは「日々患者さんと向かい合いながら共感する心,疑問を感じる心,問題に悩む心,そして創意工夫を凝らして解決しようとする心─これこそが臨床研究の出発点であり,医療に真摯に向き合う態度の現れである」.将に我が意を得たりといえよう.そう,日々の臨床経験を単なる症例として積み重ねるだけで終わらせるのでは悩み方・創意工夫が足りないのだ.医療人たるが故に持つ医の志を持って科学論文にまで具象化できて初めて,目の前の患者にも真摯に向き合ったことになると筆者は訴える.
さて,世界初となるiPS 細胞の臨床研究が2013 年日本で始まる.対象は加齢黄斑変性の患者.iPS 細胞から作った網膜細胞のシートを移植し視力の回復を試みる予定のようだ.それに匹敵するとまでは言わなくとも,日本の歯科界から多くの臨床研究成果が世界中に発信されるようになればと期待する.もちろん,その理論的中心となるのは疫学を専門の一部としている本学会会員でなくてはならない.
(口腔衛生会誌 J Dent Hlth 63: 397, 2013 掲載)