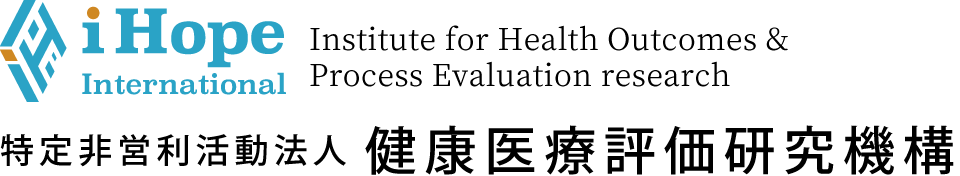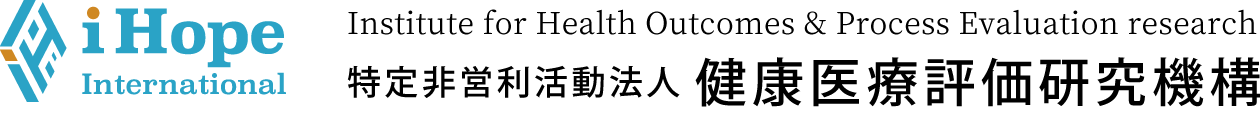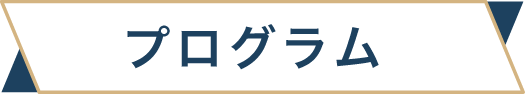事業紹介
臨床研究に必要な
理論・知識・スキルを学ぶ
10年後を見据えて医療に変化をもたらす次世代人材の育成事業

- 10年後を見据えて医療に変化をもたらす、次世代人材の育成事業です。
- 臨床研究デザイン塾は、診療実践に従事している臨床家がみずから診療上の疑問(クリニカル・クエスチョン)を検証可能な仮説(リサーチ・クエスチョン)に変換・構造化し、解析するために必要な一連の理論・知識・スキルを学ぶためのプログラムです。
- 最短でも1年はかかる大学院等のカリキュラムに参加できない多忙な臨床家に、これまでにない学習の機会を提供しています。
- 対象に応じてカリキュラムを組み立て、また修了後も継続的な学習の機会やネットワークを提供しているのが特徴です。
- 将来、各領域のニーズに応じて幅広い展開が期待されるとともに、医療の現場に対して、その成果が還元されることが期待されます。

2017年 第14回 臨床研究デザイン塾
「臨床研究
デザイン塾」
の物語
Part 1
2004年に開講した「腎臓・透析医のための臨床研究デザイン塾」は、全国の若手臨床医を対象にした集中的な合宿形式で、17年間で180名以上の塾生が参加し、1000編以上の英文原著論文が発信されています。この臨床研究デザイン塾を企画された福原俊一先生(京都大学 特任教授/ジョンズホプキンス大学 客員教授)に伺いました。

福原俊一先生
この塾は、これまで見たこともない型破りな企画であったこともあり、2004年開講当時、周りからは変わり者による変則的な活動と見られていたようです。その15年後に、日本腎臓財団から学術賞としてその価値を認めていただくとは夢にも思っておらず、まさに望外の思いでした。受賞式で数人の理事から、「学会の演題発表や質問で優れているなと感じたものは大概が塾出身者であり、塾が学界全体の研究レベルを変えた」とまで言われたことにも驚きました。
思えば、この塾は、当初より単なる知識やテクニックを教える目的で開講しませんでした。「開塾式」の塾長挨拶で、開口一番「君たちは何でこの塾に来たの?」という根源的な問いを投げかけました。塾の目指す理念や目標を塾生と共有しました。当初から目標の中に、「学界全体における臨床研究の認知と質を変える」が入っていました。先述の理事の発言から、まさにその目標が達成されたことを実感でき、感慨深いものがありました。
2022年、京セラの稲盛和夫氏が亡くなられました。これを追悼してNHKが、「100年インタビュー」という番組を再放送していました。その中で、稲盛氏は、以下のような方程式をお示しになりました。
人生の結果 =
「能力」 × 「熱意」 × 「考え方」
この方程式で、特に「考え方」という項目が興味を引きました。ベクトルと言えるかもしれません。確かに、いくら偏差値が高くても、その考え方がネガティブな方向だと、マイナスの結果が大きくなるだけだと納得できるものでした。稲盛氏が80歳を超えてから奇跡的に再生した日本航空をみても、当時の社員の多くが高い能力をもったエリート集団だったにも関わらず、この方程式の「考え方」が必ずしも良い方向を向いていなかったことが、倒産につながったのかもしれません。

2015年 第12回 臨床研究デザイン塾のグループワークの様子

2016年 第13回 臨床研究デザイン塾
塾を開講した当時、この方程式のことは知りませんでしたが、「考え方」を違う表現でこの塾生と共有したことを思いだしました。私はそれを「コア・バリュー(中核的価値基準)」という言葉で表現しました。そのコア・バリューには、「研究の科学性や倫理性で妥協しない」はもちろんのこと、「臨床現場に切実な問題を解決する研究を目指す」が入っていました。現在、塾生たちは見事にそのコア・バリューを体現してくれています。
実は塾には、hidden agenda(隠れた目標)もありました。それは「塾から教授を10人輩出して、学界の文化を変える」というものでした。果たして、2022年に入り、新たに3名もの教授が誕生し、開講以来この塾から10人の教授が誕生し目標を達成することができました。
今回は、そのうちの2人を紹介します。
一人目は、5期性の星野純一氏です。星野氏は、全国トップクラスの総合病院である虎ノ門病院で腎臓内科を専攻された方です。塾に参加後、米国UCLAに留学、大きな研究成果とともに帰国されました。帰国後も研鑽を積まれ、東京女子医科大学の腎臓内科の主任教授に就任されました。編集長が代表理事を務めている日本臨床疫学会の上席専門家としても活躍されています。今後は、次世代の臨床疫学研究者の育成に貢献していただくことを期待しております。
もう一人は、10期生の桑原篤憲氏です。桑原氏は腎臓内科の専門医でしたが、途中から学長の勧めで、2022年6月に総合診療科の主任教授に就任されました。今後の日本の医療を考える時、多くの慢性疾患を抱えること(マルチモビディティー)が当たり前の高齢者が増加する中にあって、臓器別医療とともに、総合診療も重要となります。特に地域医療においては、優れた技術と高い志を持った総合診療医が求められています。私は、地域医療支援にアカデミズムを加えて福島県、和歌山県、高知県に総合診療アカデミーを作りました。桑原氏も、今年からこの輪の中に入ってくださり、早速、研究カンファレンスにご参加いただいております。
15年以上前に開講した「腎臓・透析医のための臨床研究デザイン塾」から、未来の医療を担う教授が生まれたことは、まさに塾の誉だと心より嬉しく感じています。両氏のこれからの活躍に大いに期待するところです。
「臨床研究デザイン塾」の物語
Part 2
會津藩校日新館
臨床研究
デザイン塾
https://www.fuji-future.jp/aidujuku/
今でも続いている塾があります。それが「會津藩校日新館 臨床研究デザイン塾」、通称「會津塾」です。この塾は、福原俊一先生が、福島の大震災後の翌年、福島県立医科大学の副学長を兼務してから開始したプロジェクトの1つです。以来10年にわたり毎年開催され、これまで400名以上の臨床医が参加されています。
この塾構想の提案をお聞きになられた菊地臣一学長は即断即決されました。菊池先生なしには會津塾は実現しませんでした。2022年に亡くなられた菊地先生の偉大さを偲ぶ追悼文は以下をご覧ください。
菊地 臣一先生を追悼して
http://www.shirakawa-ac.jp/news/2022/02/08/1321/

2015年 第3回 會津藩校日新館 臨床研究デザイン塾
2013年開講当時、福島県は医療崩壊寸前の状況にあり、県外の医師に福島県のことを何とか知ってもらおうと思い発案しました。福島の温泉旅館で2泊3日、参加者が寝起きを共にして学ぶ合宿形式のイベント。参加者を5~6名のグループに分け、グループでリサーチ・クエスチョンを考案、揉み合い、最終日に研究計画を発表、最優秀賞を表彰、という塾の原点ともいえるやり方でした。
震災直後にもかかわらず全国から50名以上の臨床医が福島県に集まってくれました。夜は浴衣を着て夕食会をして懇親しますが、その後も各グループは深夜まで作業します。ほとんどが30代の家族も持っている臨床医ですが、学生のような気持ちになって議論を交わす様は壮観でした。出身地、専門、所属を超えたインターアクションが生まれました。最終発表会では、皆、緊張し神妙な面持ちでのぞみ、最優秀賞を勝ち取ったグループの喜びは予想以上のものでした。最後の懇親会では、緊張も解け、多くのネットワークが生まれるのが見えます。
興味深いことに毎年参加者の中から必ず1人か2人、本格的に臨床研究を学んでみようとする方が出てきます。その方々の中には、福島県立医科大学の臨床研究フェローシップ、白河総合診療アカデミー、京都大学の大学院に来た方もいらっしゃいます。現在、會津塾参加者の中から7名の方が、アカデミックなポジションを得て活躍されています。塾生のおひとり、土方保和先生も、北九州の病院から京都大学の大学院に入られ博士号を取得し、2022年4月から我々の仲間として研究することになりました。研究論文も目白押しです。彼の物語は、Primaria ONLINE* 2021年12月号「臨床研究の道標」や、拙著「臨床研究21の勘違い」(医学書院)をご覧ください。
*Primaria ONLINEは、医療者であればどなたでも会員(無料)のご登録でご覧いただけます。
https://primaria.pro/
塾の理念・
プログラム・成果
- わが国の臨床家による、質が高く、臨床的・社会的意義の高い臨床疫学研究を世界に発信することを推進するために臨床研究をキャリアとする若手研究者を育成すること
- 臨床研究者による新しいリサーチ・コミュニティを創出すること
- 臨床研究デザイン塾では、「漠然とした疑問」から「研究の基本設計図」までの7つのステップにそって、講義や小グループ実習を行います。
- 独自のリサーチ・クエスチョンに基づくプロトコールの作成をグループで行い、完成したプロトコールの発表を行います。
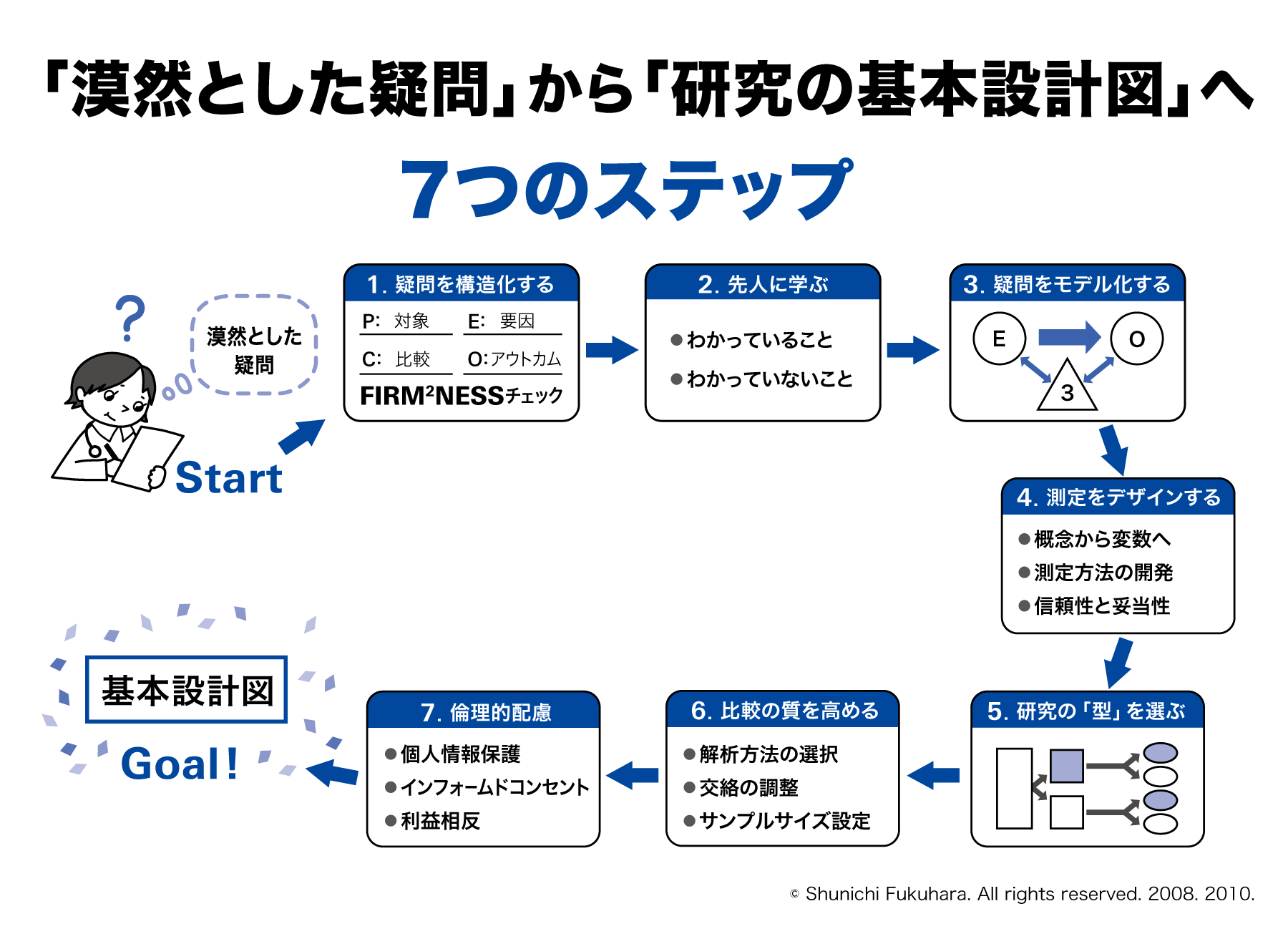
- 塾修了者の中には、大学院に入学する方、臨床研究のために海外留学する方、国際学会へ発表する方(優秀賞の受賞)、国際誌への英文原著論文を出版する方、教育研究機関の教授になる方などが出現しました。塾生同士の絆も生まれ、塾生による研究プロジェクトが企画・立案・プロトコール化されるまでに成長しました。
- 塾生による原著論文リスト(2017年時点)はこちら
-
- 塾生の教授就任者(2022年時点)*敬称略
-
- <1期生>
-
- 柴垣 有吾(聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科 主任教授)
- 濱野 高行(名古屋市立大学医学研究科 腎臓内科学分野 教授)
- 小松 弘幸(宮崎大学医学部 内科学講座 循環器・腎臓内科学分野 臨床医学教育部門 教授)
- 長谷川 毅(昭和大学 統括研究推進センター研究推進部門 教授)
- <3期生>
-
- 濵田 康弘(徳島大学医学部 医科栄養学科 臨床実践栄養学講座 疾患治療栄養学分野 教授)
- <4期生>
-
- 佐田 憲映(高知大学医学部 臨床疫学講座 特任教授)
- 土井 俊樹(広島大学病院 腎臓病地域医療学 寄附講座 教授)
- <6期生>
-
- 栗田 宜明(福島県立医科大学大学院医学研究科 特任教授)
- 星野 純一(東京女子医科大学 内科学講座 腎臓内科学分野 教授)
- 遠山 直志(金沢大学附属病院 先端医療開発センター 生物統計部門 特任教授)
- <10期生>
-
- 桑原 篤憲(川崎医科大学 総合臨床医学 主任教授)