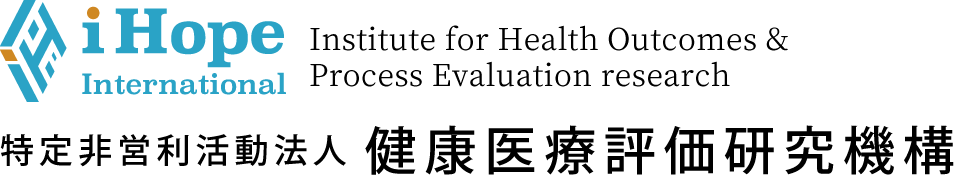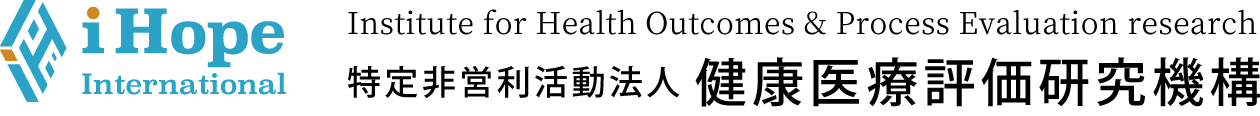NEWS
第12回 多職種のための臨床研究てらこ屋[オンライン]~臨床研究のはじめの一歩を“正しく”踏み出そう~ 2025年9月28日(日)13:00~17:00 開催のお知らせ

第12回 多職種のための臨床研究てらこ屋[オンライン]
すべての医療職で取り組む、リサーチ・クエスチョンを突き詰める1Dayワークショップ
*「第12回 多職種のための臨床研究てらこ屋」のお申し込み受付は終了いたしました。多数のお申し込みをいただきまして、ありがとうございました。
「多職種のための臨床研究てらこ屋」は、医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師、鍼灸師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、介護福祉士など、医療者が職種の垣根を超えて臨床研究の本質に取り組む稀有なオンラインワークショップです。
臨床研究において何よりも重要なのは、「リサーチ・クエスチョンの作り方」です。このステップを適切に進めなければ、どんなに最先端の統計手法を駆使しても、間違った結論にたどり着いてしまいます。
「多職種のための臨床研究てらこ屋」では、グループワークを主体に「リサーチ・クエスチョンの作り方」に、とことん向き合っていただきます。毎年コンテンツも変わっていますので、過去にご参加いただいた方も大歓迎です。
【日時】
2025年9月28日(日)13:00~17:00[オンライン開催]
【対象】
医療職なら誰でも可
【塾長】
福原 俊一[京都大学 特任教授/ジョンズホプキンス大学 客員教授]
「臨床研究の道標 -7つのステップで学ぶ研究デザイン-」著者
【講師】
紙谷 司[京都大学医学部附属病院 臨床研究教育・研修部 特定講師/理学療法士]
土方 保和[京都大学大学院 地域医療システム学 臨床疫学グループ 特定講師]
【ファシリテーター】
多職種(医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士など)で構成されるファシリテーターが学習をサポートします
【プログラム】
<てらこ屋の達成目標>
・研究計画を作成する7つのステップ(福原塾長提唱)のうち「ステップ1.疑問を構造化する」「ステップ2.先人に学ぶ」「ステップ4.測定をデザインする」を習得する。
・魅力的なリサーチクエスチョン(RQ)にするための新規性や測定のポイントを理解する。
・AI(ChatGPT×Consensus)を用いた効率的な文献検索が行えるようになる。
<事前学習>
・福原塾長らによる研究デザインの動画講義の視聴
・ワークショップの効果を最大化するための個人ワーク
<当日>
・事前学習のおさらい講義
・魅力的なRQを目指して取り組むグループワーク
・グループワークの成果について参加者全員でディスカッション
・てらこ屋修了者が伝える、RQが論文として成就するまでの苦節物語(特別講義)
*内容は変更となることがあります。予めご了承ください。
【参加費】
5,000円(税込)
【受付締切】
2025年9月12日(金)
2025年9月19日(金)※延長いたしました
【申込方法】
*以下よりお申し込みください。定員になりしだい締め切ります。キャンセル待ちは受け付けておりません。
https://2025tashokushu.peatix.com/
【主催・お問い合わせ】
特定非営利活動法人 健康医療評価研究機構[iHope International]
多職種てらこ屋 事務局
———-
【セミナーの受講規約につきまして】
参加費のお支払い後に受講者のご都合によりご参加を辞退される場合でも、原則的に参加費の返金はいたしません。お申し込みいただく前に「セミナー受講規約」をお読みください。
【個人情報のお取り扱いにつきまして】
お申し込みに際し、みなさまよりご提供いただきました情報は、個人情報保護法に則り、以下の目的の範囲内で特定非営利活動法人 健康医療評価研究機構にて適切に管理いたします。
<個人情報の利用目的>
ご本人の確認、セミナーのご案内やアンケート調査、お問い合わせやご相談へのご回答、その他の弊機構サービスのご案内を目的とします。
弊機構は、みなさまの個人情報を第三者に開示・提供することはいたしません。
なお、セミナー開催中に事務局にて映像、写真による記録を行い、広報のため報告書やホームページなどに掲載することがあります。予めご了承ください。
「個人情報保護に対する基本方針」
【領収書の発行につきまして】
領収書の発行につきましては「領収データにアクセスする」をお読みください。
———-
【参加者の声】
京都大学医学研究科 博士課程 開地 亮太先生
私にとって、多職種のための臨床研究てらこ屋(てらこ屋)は、「研究を始める楽しさ」を教えてくれた場です。その中でも、特に印象に残っている2つの価値を紹介します。
1つ目は、疑問を整理し、研究につなげる考え方が身につくことです。てらこ屋では、日常臨床で生じる疑問をクリニカルクエスチョン(CQ)からリサーチクエスチョン(RQ)へ磨き上げる方法を学びます。「漠然とした疑問をどう整理し、研究に活かすか」という視点が得られるのが大きな魅力です。臨床シナリオをもとに、親切なサポートを受けながら、自分達で疑問を整理し、研究として形にしていく体験ができます。私自身、この学びを通じて、何が分かっておらず、何を知るべきかを整理する力がつき、日々の臨床でCQを意識する機会が増えました。メモに書き留めるCQの数も大幅に増えています。
2つ目は、異なる専門性を持つ参加者と議論するスキルを学べることです。てらこ屋では、構造化されたRQをもとに議論を進めることで、専門性の違いを超えた建設的な対話が自然に生まれます。たとえば、「対象者・曝露(要因)・アウトカム」のどの部分について議論をしているのかが明確になるだけで、多職種がそれぞれの強みを活かし、意見を持ち寄ることができます。こうして新たな視点が生まれる瞬間は、てらこ屋の醍醐味のひとつであり、非常に刺激的なものです。
最近、「研究に興味はあるが、何から始めればよいかわからない」という声をよく聞きます。そんな方にこそ、てらこ屋を知っていただきたいです。今年も、多くの方と意見を交わし、新たな視点を得るのを楽しみにしています!